1958年生まれ、ドイツ・ゲミュンデン出身。80年代にドキュメンタリー映画の脚本、監督、撮影、編集の技術を独学で習得する。その後、ニュルンベルクでインディペンデントのフィルムメーカーのグループを結成。文化や歴史、社会的なテーマを扱ったドキュメンタリーを数本手掛ける。1983年には、ライナー・ホルツェマー・フィルム・プロダクションを設立。これまでに30本以上のドキュメンタリー映画やアーティストのポートレイトを制作する。日本での公開作品は、『マグナム・フォト 世界を変える写真家たち』(99年)や『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男』(16年)など。
『マルジェラが語る “マルタン・マルジェラ”』ライナー・ホルツェマー監督インタビュー
匿名性を貫いた謎の天才デザイナー! 知られざる真実が明らかに
#デザイナー#ファッション#マルジェラが語る “マルタン・マルジェラ”#ライナー・ホルツェマー

決して希望を捨てることなく、説得し続けた

2021年9月17日より全国順次公開
(C)2019 Reiner Holzemer Film – RTBF – Aminata Productions
世界で注目を集めるファッションブランド「メゾン マルタン マルジェラ」を作り上げたにもかかわらず、公の場には一切姿を見せることなく匿名性を貫いてきた“天才デザイナー” マルタン・マルジェラ。これまであらゆる取材や撮影を断り続けており、その全貌は謎に包まれていた。そんななか、「このドキュメンタリーのためだけ」という条件のもとで完成したのが『マルジェラが語る “マルタン・マルジェラ”』。
本作ではキャリアに対する知られざる思いやクリエイティビティについて、マルジェラ自身の言葉によって語られる貴重な機会に触れることができる。そこで、取材不可能とされていたマルジェラの信頼を勝ち取った秘訣や制作の裏話について、ライナー・ホルツェマー監督に話を聞いた。
・“柔らかい足袋にヒールをつけてみようか” マルジェラが語る足袋ブーツの誕生秘話!
監督:僕は『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男』で初めてファッションの世界を撮ったんだけど、僕にとってファッション業界はすごく興味深いところなんだ。極めて視覚的でクリエイティブな世界だし、働いている人たちは、すごく波乱万丈で面白い人生を送っているからね。
だから2作目を撮ろうと思ったとき、ドリス(・ヴァン・ノッテン)に匹敵する新たな主人公を探し始めることにしたんだ。そして、2017年に『ドリス・ヴァン・ノッテン ファブリックと花を愛する男』の上映会に出席した日、ちょうどアントワープのモード博物館(MoMu)で、ある展覧会のオープニングをやっていた。それが、エルメス時代のマルタン・マルジェラの作品を中心としたものだったんだ。

監督:15年前の作品群なのに古さを感じさせず、すごくピュアで、極めてエレガント。僕は彼が生み出したガーメント、装い、そしてコレクションの虜になったよ。展覧会の隣には、趣がまったく異なるマルタンの服が何着か展示されていたけど、そちらは刺激的で、ラディカルで、アヴァンギャルドなファッションだった。モデルの顔をベールで覆い、トップスは透明。これが同一人物の作品なのかって信じられなかったよ。
というのも、ほとんどのクリエイターは、1つのアイコニックなアイデアを手を変え品を変え、生涯に渡って使い回すからね。彼をもっと知りたくなった僕は、展覧会のカタログを買ったんだけど、シュールな反面、自然にデザインやコレクションの服に目線を向けさせるのが彼のやり方なんだと思った。あのアプローチのすべてが、僕はすごく気に入ったんだよ。
監督:ファッション業界に強いコネクションを持っている共同プロデューサーのアミナータ・サンベに「次の主人公が見つかったかもしれない」って伝えたんだ。そうしたら、彼女にこう言われたよ。「せいぜい夢を見てなさい。絶対に無理だから」って。なぜなら、彼は30年もの間、映画や写真に撮られることなく、インタビューも拒絶してきていたからね。だから、最初は残念だけどこのアイデアを諦めざるを得なかった。でも、展覧会のカタログを眺めながら、「彼と接触する方法があるはずだ」と考え続けたんだ。
監督:運がよかったのは、彼がパリでの展覧会を準備中だったこと。僕は展覧会のキュレーターにメールを書いて、マルタンへメールを回してもらえないかと頼んでみたんだ。でも、返信は何ヵ月も来なかった。だから、また頼んでみた。多くのフィルムメーカーが彼の映画を撮りたいと思っているから、この類のメールはたくさん届いているんだよね。
実際、僕の2通目のメールが彼の手に渡ったとき、他の多くの人も接触していた。ただ、幸いなことに、マルタンが信頼を寄せる人たちが僕の『ドリス・ヴァン・ノッテン』を見てくれていて、最高の組み合わせだと彼に助言してくれたんだよ。最初のメールを出してから半年後、ついに返信が来た。そしてマルタンは、「もしまだ映画作りに興味があるのなら、会わないか」って書いてきたんだ。

監督:もちろん不安でたまらなかったけど、僕らはパリで会うことにした。部屋にいたのは、女性1人と男性2人の合わせて3人。でも、僕はマルタンの風貌をまったく知らなかったんだ。かなり若い頃の写真が数枚しかなかったからね。
マルタンは単刀直入に話を始めたんだけど、初めて会ったとは思えなかった。そのときに僕が展覧会を撮影することを了承してくれたので、翌週から美術館の地下ですべてのガーメントを使って、撮影準備を始めたんだ。僕としてはテスト撮影のつもりだったけど、考えていたのはいったいどこまで踏み込めるだろうかということ。一方で彼は、ポートレイト・ドキュメンタリーについては、話したがらなかったよ。単に展覧会を誰かに撮ってもらいたかっただけだったんだ。
監督:そうだね、僕は決して希望を捨てなかったよ。一旦、一緒に仕事を始めて、お互いのことをよく知り、彼が僕の作品を見てくれれば、きっと僕を信用してくれるはずだと信じていたんだ。そのためにも、我々が決断する決定事項の一つ一つに彼に関わってもらうことが僕にとって極めて重要だった。そうすれば彼が打ち解けて安心するとわかっていたから。
だから、「ドキュメンタリーはすばらしいものになる」と僕はずっと映画製作を提案し続けた。するとマルタンは、自分が話さず、顔も出さない場合、どんなことが出来るかと尋ね始めたので、そこで僕らは様々な話し合いを重ねて、テスト撮影を開始したんだ。
撮影中に僕がいろいろ質問をすると、彼は答え始めるようになり、これが映画に向けた出発点。ついに彼が「イエス」と言ってくれたんだ。「ドキュメンタリーを撮ることに同意する」という手書きの小さなメモをくれたときには感激したよ。
監督:まず必要なのは、長いプロセス。そして、相手に対して極めて誠実であることだね。あとは自分がやりたいことを相手に話し、自分のことを信頼できるように説得するのもすごく重要なこと。
そのほかにも、一般に公開する前に作品を見せることを最初に約束し、気に入らないところがあれば、変更する権利もあることも伝えるようにもしているよ。ただ、そうは言っても、主人公の希望に盲目的に従うことはしない。もし映画の中で重要な部分だと確信していたら、残すと主張もする。たとえば『ドリス・ヴァン・ノッテン』では、ドリスがあまりにもプライベートな部分だと感じるシーンが2箇所あった。だけど僕は観客に彼の人間性を見せる重要なシークエンスだと説得。結果的にドリスは僕を信頼してくれて、そのシークエンスは残すことになったんだ。
監督:何よりも相手と親密になり、信頼関係を築くことが大事。誠実な態度で臨み、策を講じたりしないことだね。さらに、信頼を築こうとしているときには、大人数の撮影クルーを組まないほうがいい。限りなく小規模にすべきだと思うよ。特に相手がシャイであるときや公に顔をさらけ出したくない場合は、なおさらだね。今回も、僕1人だけというときもあったほどだから。
信頼関係において大事なのは、とにかく誠実であること
監督:最大の難関はマルタンから話を聞き出すことだったが、そういうときに助けとなったのは時間。マルタンともドリスとも、長い時間を一緒に過ごすようにしたんだ。常にカメラを肩に抱えてね。そうすると、あるときから彼らは僕が手ぶらなのか、それともカメラを持っているのか気にしなくなるんだ。
マルタンの場合も、ドリスを撮影したときと同じやり方で、誰も邪魔することなく撮って撮って撮りまくった。徐々に僕の存在を気にかける人はいなくなったので、仕事の手を止めさせず、話したいときに話してもらうようにしたよ。
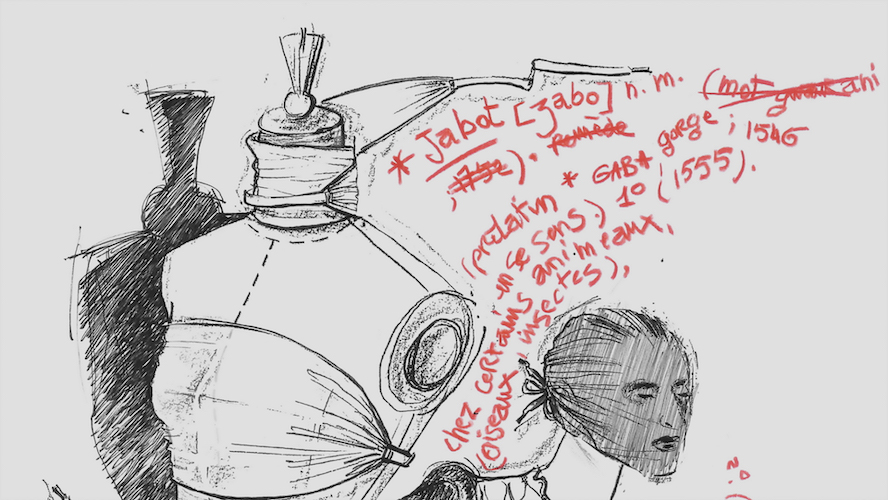
監督:今回の場合、インタビューを受ける形を望んでいないことは分かっていた。というのも、マルタンは一度もインタビューを受けたことがなかったからね。でも、あるときから彼は僕といることを居心地良く感じてくれたようで、パリの彼の自宅にあるスタジオで、自分のキャリアや子ども時代の話を始めたんだ。
なかでも、祖母の絵画がマルタンには重要な意味を持っていた。だから、彼は映画のためにその絵を用意してくれて、前日の夜に自分が言いたいことを文章にまとめて準備もしてくれた。そして、彼はカメラの前でそれを読みたがっていたんだ。でも、どうしても“読んでいる感”が出てしまうから、それは難しいと伝えたんだけど、マルタンから試させてほしいと。
朗読の後、「どう思う? どんな具合だった?」って聞いてきたけど、僕は読んでいる感じに聞こえるし、思いに任せて自由に喋っている感じがしないと言ったよ。すると「今度は、もっとうまくやるからもう一度録音してほしい」と言ってきた。でも、やっぱり読んでいる感じだと答えた。
監督:僕の意見に納得した彼は、ちょっとした絶望感を味わっていけど、僕はごく単純な話だと持論を話した。そこで、彼にワイヤレスマイクを付けることを提案して、いつでも録音できるようにしたんだ。最初、彼はちょっと不安そうだったけど、すぐにマイクの存在を忘れて、2日後には「話したいことがあるんだけど、カメラは回っているのか」とか聞いてきた。あれはすばらしい体験だったね。イヤホン越しに彼の力強い声を聞くことができて、僕にとっても彼にとってもすごく幸せな時間になった。そして何より、彼は美声の持ち主だったよ。
監督:最初の頃から、マルタンは顔を撮られたくないと言っていたので、他の映像が必要だった。そんなとき、撮影していた絵画やバービー・コレクションやデザインのスケッチを見せるときの彼の手を見ていたら、すぐに彼の手の動きにある種のエレガンスがあることに気づいたんだ。
監督:彼はネガティブな経験に対して身体的に反応する人なので、仕事を辞めてから体の不調を解消するのに1年かかった。彼が長年抱いていた後悔のひとつは、別れを告げることなくアトリエを去ったこと。彼にとって非常に辛いことだったんだ。私は「その経験を語ってほしい」と言い、彼は映画の後半でチームに手書きのメッセージで感謝を送った。最終的には、人々が彼に会ったような、あるいは彼を見たような感覚を持つことができるのではないかと思うよ。
監督:最終的には撮影した映像は、200時間にも及んでいたよ。マルタンはごく最初から映画制作やあらゆる決定に関わっていたので、もちろん編集作業にも関わることも望んでいた。でも、編集は僕が1人でやらなきゃダメだと主張したんだ。なぜなら一歩引いて、この映画をどんな風に見せるべきかを練る必要があったからね。だから映画をどう構成すべきかを映像を見て考える時間が必要だと彼に言ったんだ。
僕は4ヵ月間、映像と格闘し、その間はマルタンとは一切連絡を取らなかった。電話もメールもしなかったほど。人づてに彼がすごく不安視していることは聞いていて、みんなから、どうして彼を編集に関わらせないんだと聞かれたけど、「ますます混乱するからダメなんだ」と答えた。僕には、1人で考える時間がどうしても必要だったんだ。マルタンは主人公だけど、フィルムメーカーじゃない。もちろん蚊帳の外に置かれるのは、彼にとって辛いことだけど、僕のものの見方は誰にもできないことなんだ。

監督:編集を始めて4ヵ月後、彼を招いてラフカットを見てもらったんだけど、あのときはすごく緊張したよ。前日、ミュンヘンに到着したマルタンと夕食を食べながら「どんな風にラフカットを見てほしいんだい?」と聞かれた瞬間を忘れることはないだろうね。というのも、僕らが映画を止めながら解説しながら見てゆくのか、それとも冒頭から最後まで映画を見せるのか彼は気にしていたんだ。構成順も見てほしいから、僕はいつも最初から最後まで見せるようにしている。
彼は一言も発することなく、モニタの前にまるで小学生みたいに背筋をピンと伸ばして座っていたよ。そして上映が終わると、僕をハグしてくれたんだ。いかに心を打たれて感激したかをまくし立てて、感謝してくれた。あの瞬間は僕もすごく嬉しくて、ジーンとしてしまったよ。
監督:……と思ったら、次の瞬間いつものマルタンに戻って「細かく詰めていこう」と。そして、彼が変更すべきだと思う箇所について話し始めたんだ。分単位のリストを作り上げ、変更を望んだ箇所はなんと120以上。ただ、僕はいつものごとく、変える必要はないと言ったんだ。この時点ではあくまでラフカットであって、編集作業が完了したわけではなかったけどね。数週間後、僕らはミーティングで段階を踏みながら、ファイナルカットが完成させたわけだけど、すごくいい協力作業だったよ。
監督:フィルムメーカーとしては自分のアイデアと戦わなければならない一方で、対象者である主人公をぞんざいには扱ってはならないということ。最終的に、相手に「そうだよ、これが僕のポートレイトで、僕の人生だ」と言わせたいからね。
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
【ゲスト登壇】『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』プレミアム先行試写会に10名様をご招待!
応募締め切り: 2025.04.22 -
【キャスト登壇】DMM TV オリジナルドラマ『ドンケツ』完成披露試写会に30組60名様をご招待!
応募終了: 2025.04.15






































