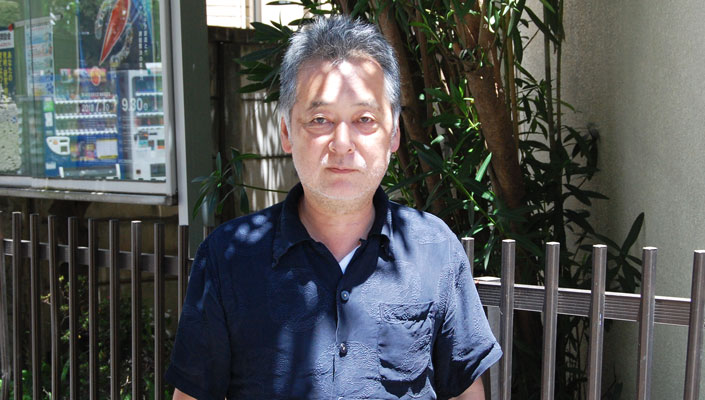1960年生まれ、大分県出身。京都大学哲学科在籍中より、8ミリ、16ミリなどで自主映画を製作。卒業後、獅子プロダクションに所属し、助監督に携わった後、1989年にピンク映画『課外授業 暴行』で監督デビュー。1997年『KOKKURI こっくりさん』で一般映画デビューし、以後はテレビドキュメンタリーなどにも活躍の場を広げる。 Gackt主演、HYDE出演の『MOON CHILD』(02年)、妻夫木聡主演の『感染列島』(09年)などを手がけ、4時間38分の長編『ヘヴンズ ストーリー』(10年)をインディーズ体勢で制作し、第61回ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞とNETPAC(最優秀アジア映画)賞を受賞。日本国内でも芸術選奨文部科学大臣賞映画部門を受賞。『64 –ロクヨン− 前編』(16年)では第40回日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞。今年は生田斗真、瑛太主演の『友罪』(18年)も公開された。
大正末期、関東大震災直後の混沌の中、東京近郊にやって来た女相撲一座が、「格差のない平等な社会」を標榜するアナキスト・グループ「ギロチン社」と出会う。興味本位で見物に来た「ギロチン社」中心メンバー、中濱鐡と古田大次郎が女力士たちに共感、共に激動の時代を駆けていく情熱を描いた『菊とギロチン』。『64 –ロクヨン− 前編/後編』や『友罪』などを手がけた瀬々敬久監督が、20代の頃から構想を温め、ついに完成させた作品について語った。
監督:いや、バブルを味わってないんで。僕はピンク映画の助監督でしたから、逆に悪くなっていく一方。当時はアダルトビデオが台頭してきて、いわゆる成人映画は凋落の一途をたどる感じだったんです。状況はどんどん悪くなる、でも何かしたいという思いはあるわけです。その辺りでシンパシーがあったってとこだと思うんですけど。
監督:そうです。まさにそうですね。(出身校である)京都大学に西部講堂という自主管理の空間があって、僕はそこで自主上映とかやっていたんです。上下関係なく、先輩も「さん」付けせずに全員呼び捨て。そういう雰囲気もギロチン社のアナーキズム的なところとよく似てましたね。
監督:95年当時のはもう少し牧歌的な青春映画っぽい話でした。ギロチン社の男性たちと女相撲の女性たちが出会って、最終的には権力と闘うという骨子は同じです。でも、3.11の震災以降にもう一回調べ直したんです。共謀罪とか特定秘密保護法とかができて、どんどん締め付けがきつくなる世の中になっていったので、戦前の流れとすごく似てると思うところもあった。そこで、大正から昭和の自警団について調べると、在郷軍人会が構成員をしていたというので、その組織についてさらに調べて。映画の舞台になる関東大震災後、東京には住む場所がなくて、中濱たちは千葉県の船橋に仮住まいするんですが、近くには習志野の陸軍駐屯地があった。そこで起きていたことについては証言が結構残っていて、映画の中で描きましたが、そこが震災以後に加えた部分です。
今しかできない、今やるしかないという思いと、一番最初に映画を作りたいと思った時の気持ちですね。自主映画という形で、誰に頼まれるわけでなく、自分たちで作っていく。もう一回そこに立ち返って、そういう初期衝動で映画を作りたいと思ったんです。一方、そんなに小難しいこと考えて作るのではなく、エンターテインメントとしての青春映画という面を押し出しつつも、今の状況で必要とする内容であると思ったので、そこは無理してでも作ったところはあります。
監督:それは大きいですね、やっぱり。主人公の花菊は、「女相撲なんかエロだろ」と言われると、「よしんばエロだって何が悪い」って答えるんですね。一般的に「それ、エロじゃないの?」というフィルターが掛かるわけですよ。ピンク映画には当然そういう目的もあるけど、そこに参加してる女優さんたちは、そこで自分たちの自己実現を果たしてるわけです。撮影の現場として、ものを作ることは楽しいし、すごく貧しくて予算がないとしても、同志的な雰囲気の中で自己実現ができる。エロスが売りだとしても、自分たちが得るものがある。その感じは女相撲の世界観とよく似てると思いますね。
監督:不器用そうだけど、自分を何とかしたいという思いが伝わったってことですかね。2人ともオーディションで選びましたが、そこが強いなと。木竜さんに関しては、ちょっと懐かしい昭和顔で、不器用さの中に強さを感じました。寛一郎に関しては、これが初めての出演で、芝居もできなかったけど、存在感とオーラはやっぱりあったんですよ。そこに賭けようと思いました。
今回は一般の方から出資を募ったりカンパで資金集めをして作って、そういう思いの集結で作る映画だから、キャストに関しても経験とか有名とか関係ない部分から始めてみようという気持ちがありました。映画の作り方自体、方法自体が、もう既に表現である、そういう発想でした。
監督:生きることに慣れてるっていうか。韓さんは資金集めと出演者募集のホームページを見て、「この映画に出たいです」と自ら志願してきたんです。中濱役はオーディションしてもなかなかいい人がいない。そんな時に、韓さんと同様に自ら志願して出演が決まったのが山田真歩さん(小桜役)で、東出さんは山田さんと同じ事務所だったんです。台本を目にした事務所の方から、東出さんのスケジュールが空いている、と。彼自身がすごく歴史好きで、興味を持ってくれて。ラッキーなんです、ここに関しては。
それに東出さん自体が実はすごく男っぽい人なんです。そういう気質が中濱と合っていたと思います。あとカリスマ的なところもありますもんね。
監督:だらしなくて駄目な人たちですね。
監督:だまされやすいっていうか、人が良いっていうか。
監督:しますね、それは。やっぱ最終的に人が良いわけじゃないですか。人が良い分、すぐ他者に共感できる。女相撲の人たちにもすぐ共感するわけでしょ。それは今、大切なことだと思うんですよね。人に共感すること。それができない世の中になってきてるじゃないですか。いい加減だけど、人に共感して一緒に戦おうと思う。それが彼らなんです。それはすごく大切なことだと思います。
監督:そうですね。でも若干違うのは、大西君が演じている彼は、実は経験者であること。妄想しているだけじゃなく、戦争のつらさもあり、自分たちがパージされた経験もあって、その怒りを違う方に向けたりするわけですよね。そういう意味では、現代の排他主義的な人々とは違うと思うんですね。経験せずに全部仮想の中で言っているのとは全然違うと思いますよ。
監督:それはありました。大いにありましたけど、あの時はいわゆるDVD会社や弱小でも映像関係の会社からいろいろ出資していただけたんです。まだDVDとか売れてた時代なんで。今はその状況も違う。今回はたとえば美術やCGの部分で現物出資ということで皆の協力があったことも大きいです。
監督:関東近辺にはあんな風景は残っていないので、京都や滋賀で撮影できたこと、実際に松竹の京都撮影所を一部使わせてもらったのも大きいです。そこの美術や衣装のスタッフが参加してくれました。普段、定番の時代劇をやっている彼らにすると、こういう企画が来ると楽しいわけです。すごく乗ってくれていろんなアイデアも出してくれるし、やってくれる。僕らみたいな東京から行くチームと合体して、また違う化学反応を起こすこともあったと思います。
監督:何回も言いますが、僕が20代の時に思いついた企画です。当時自分はこういう映画を作りたかったんだなと見終わった時思ったんですね。そういう意味では若い人の映画だと思うんです。鬱屈してたり、何とかしたいと思ってる人たちが、「こういうふうに生きたい」というところを表してる映画だと思うし、そう感じていただけるように作ってるつもりなので、ぜひともそういう人たちに感じてほしい。今いろいろもがいてる人たちに見てもらって、何かを持って帰って、また何か切り拓いてほしいなって。上から目線じゃなく、そういうところにつながっていけばいいなとは思っています。
(text:冨永由紀)
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
【ゲスト登壇】『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』プレミアム先行試写会に10名様をご招待!
応募終了: 2025.04.22 -
【キャスト登壇】DMM TV オリジナルドラマ『ドンケツ』完成披露試写会に30組60名様をご招待!
応募終了: 2025.04.15